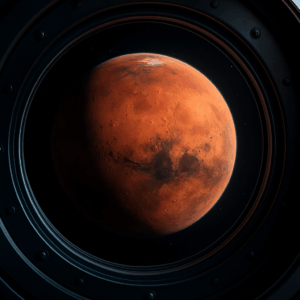注意)この物語はChatGPTとの共作です
佐伯悠真(さえき ゆうま)編
駅前の路地裏に、陽の届かない薄暗い喫茶店があった。 看板には「喫茶・パ…レル」とあるが、文字は半分ほど剥げ落ち、残りは黒ずんで判別がつかない。
僕はその朝、会社へ向かう途中で迷い込んだ。どのチェーン店も満席で、仕方なく開いた古びた扉。
かすかな鈴の音が鳴ったが、それは金属の音ではなく、まるで遠い鐘の残響のようだった。 カウンターには白髪交じりのマスターが立っていた。
背筋は直立し、目だけが奇妙に深い。
まるで時計の針の影のように動かない表情で、低く言った。「……お好きな席へ」 差し出されたメニューには、ありふれた珈琲の名に混じって、奇妙な文字が踊っていた。
──「昨日の後悔ラテ」「もしものカプチーノ」「未来の気分エスプレッソ」。
怖いもの見たさで、「昨日の後悔ラテ」を頼んだ。 湯気に口を近づけた瞬間、胸が締めつけられる。
昨日の会議。配布資料を取り違え、同僚の失望の目、上司のひきつる顔。
その光景が鮮明に蘇る。手のひらにまで冷たい汗が滲む。 しかしカップを空にした途端、胸の奥で何かが剥がれ落ちるように軽くなった。
代わりに、背中に小さな爪痕のような痛みだけが残った。「当店の飲み物は、心を整える作用がございます」 マスターはコップを拭きながら無表情のまま言った。
マスターの声は妙に規則的で、時を刻む振り子のように聞こえた。
なんだ?この店は…でも
何故か飲むのが止められない
次に「もしものカプチーノ」。 一口含んだ瞬間、世界は水面のように歪んだ。 僕は学生服を着ていた。校舎の廊下を抜けると、そこには高校時代の彼女が立っている。
「ねえ、帰りに寄り道しない?」 当時、言えなかったはずの誘いが、甘い笑顔とともに差し出された。
僕は頷き、並んで歩いた。夕暮れの坂道、心臓の鼓動がやけに眩しい。
──だが、カップの底が見えた瞬間、世界は砕けるように崩れた。
消えゆく彼女が、最後に振り返って囁いた。「後悔ばかりじゃ、未来まで失うよ」 戻ってきた店内で、僕の指はまだ彼女の温もりを探して震えていた。
「もしもを長く味わうと、戻れなくなります」 マスターの声が、今度は警告の鐘のように響いた。
これが俺の後悔なのか…
最後に「未来の気分エスプレッソ」を頼んだ。 苦い香りが鼻腔を刺し、瞼の裏に映像が現れる。 痩せ細った未来の僕。 狭い会議室の隅で、空っぽの目をしながらコーヒーをすすっている。 その姿が、突然こちらを見返した。『……まだ間に合う』 唇が確かに動いた。
未来の自分と目が合った瞬間、心臓を氷で刺されたような衝撃が走る。 映像が霧散すると、マスターが低く告げた。
「未来は苦い。だが、その苦味を呑み込んだ者だけが、味を変える権利を持つ」
額を押さえ、息をつく。 気づけば、昨日の後悔も、過去の甘さも、未来の苦さも、ひとつに溶け合っていた。 外に出ると、朝の光が思いのほか眩しい。
振り返った瞬間、店の姿はもうなかった。 ただ、背広のポケットの内側に、見覚えのないチケットが差し込まれている。
──「喫茶・パラレル 一杯分 有効期限なし」。 指先が震える。
これは救いか、それとも罠か。
僕は深く息を吸い、背広を正して歩き出した。
どちらであれ、次に選ぶ一杯は、もう“後悔”ではないはずだから。
水城 彩花(みずき あやか)編
会社帰り、彩花は路地裏で足を止めた。
そこにあったのは、見慣れない喫茶店。
「喫茶・パラ…ル」と掠れた文字で書かれた看板。昼間は何度も通ったはずなのに、こんな店があった記憶はない。
胸の奥に小さな棘が刺さっているような一日だった。上司との意見の衝突。恋人からの「距離を置こう」というメッセージ。帰り道を歩いても、心は重くなるばかり。
気がつけば、彼女はその喫茶店の扉を押していた。
中は静かで、カウンターの向こうに背の高いマスターが立っていた。表情は変わらず、ただ静かに「お好きな席へ」と告げる。
差し出されたメニューには、見覚えのある名前が並んでいた。
「昨日の後悔ラテ」「もしものカプチーノ」「未来の気分エスプレッソ」――。
「……何なの、この店」
彩花は呟いた。だが心の奥で、奇妙な直感が囁いていた。今の自分には、ここが必要だと。
彼女が選んだのは「涙のモカ」だった。
カップを口にした瞬間、瞼の裏に過去の光景が溢れ出した。
それは幼い頃の自分。両親が激しく言い争っているのを、押入れの隅で震えながら聞いていた夜。
大学時代、夢を語る自分を「そんなの無理よ」と笑った友人の顔。
社会人になってから、誰にも言えずに抱え込んだ悔しさ、孤独。
飲み進めるほど、胸の奥に積もった涙が溶け出すように溢れてくる。気がつけば、彩花の頬を本物の涙が伝っていた。
「……ずっと泣きたかったんだ、私」
誰にも見せない強がりを、この店はあっさり見透かしてきた。
マスターはただ静かに言った。
「涙は、捨てるためにあるのではありません。抱えてきたものを確かめるためにあるのです」
涙を拭った後、彩花はふと別のメニューに目を留めた。
「選ばなかった道のマキアート」。
怖い気もしたが、惹かれるようにそれを注文した。
ひと口含むと、世界が揺れ、彩花は別の自分の人生を見ていた。
そこでは、彼女はデザイナーとして海外に渡り、鮮やかな舞台の上で自信に満ちた笑顔を浮かべていた。
一方で、別の選ばなかった道では、結婚して子どもを抱く姿。幸せそうに家庭を築き、笑う自分。
――どちらも、今の自分ではない。
現実の彩花は、仕事に追われ、恋人との関係も崩れかけ、立ち止まっている。
「……どうして私は、この道を選んだんだろう」
呟いた時、舞台の上の彩花と、母親になった彩花が同時に振り返り、同じ言葉を放った。
「あなたが今ここにいるのは、間違いじゃない」
その声は、胸を鷲掴みにするような力で響いた。
視界が揺らぎ、現実に戻る。カップは空になっていた。
彩花はテーブルに震える手を置き、呼吸を整える。心の奥で、何かが確かに動いたのを感じた。
「……未来を、飲んでみるべきかな」
彼女は小さく笑い、「未来の気分エスプレッソ」を最後に注文した。
黒い液体を飲むと、鮮烈な映像が走る。
そこには、今よりも少し大人びた彩花が映っていた。確かに疲れてはいるが、目は強く、何より堂々としている。
そしてその未来の彩花は、視線をこちらに向け、真っ直ぐに言った。
「泣いたから、選べるんだよ」
その言葉が、彩花の胸を突き抜けた。
気がつけば、喫茶店の扉の前に立っていた。外の街は変わらないが、胸の中の重さは確かに軽くなっていた。
振り返ると――店はもう、跡形もなく消えていた。
彩花は深呼吸し、歩き出す。
彼女の背筋は、先ほどよりも少しだけ、しなやかに伸びていた。
喫茶店が繋いだ想い
金曜日の夜。佐伯悠真は会社帰りの電車に揺られていた。
窓に映る自分の顔は、相変わらず冴えない。数日前に訪れた「喫茶・パラレル」で体験した出来事が、まだ胸の奥に残っていた。
“もしものカプチーノ”で見た幻――。
そこに現れたのは、高校時代に想いながらも告白できなかった彼女だった。
あの幻はただの空想だったはずだ。だが妙にリアルで、彼女の声や仕草まで鮮明に蘇る。
――もしもあの時、告白していたら。
その後悔を、ずっと胸にしまい込んでいた。
改札を抜けると、冷たい夜風が頬を打つ。帰路を急ごうとしたその時だった。
視線の先に、見覚えのある横顔があった。
駅前の人波の中に立っていたのは、水城彩花だった。
彼女の顔を見た瞬間、悠真の心臓は跳ね上がった。
――間違いない。高校の頃、想い続けた人だ。
ただ、声をかける勇気が出なかった。まるで十数年前と同じだ。
彩花はスマホを見つめていて、ふとため息をつく。その表情には、どこか影があった。
この機会を逃したらもう会えないかもしれない…
気づけば、悠真の足が動いていた。
「……水城、さん?」
名前を口にした途端、彼女の瞳が大きく開かれた。
「……佐伯くん?」
その声には、驚きと、どこか懐かしさが滲んでいた。
互いに少しぎこちなく笑った。十年以上の時を経て、再び目の前に現れた存在に、何を言えばいいのかわからなかった。
二人は駅近くのカフェに入り、久しぶりの会話を交わした。
近況を語る中で、ふと彩花が「不思議な喫茶店に行ったことがある」と口にした。
「路地裏にあって、看板は掠れてて……」
「……パラレル?」
思わず悠真が口を挟むと、彩花は息を呑んだ。
「行ったの? あなたも?」
声が震えていた。
二人の間に一瞬、言葉にならない沈黙が落ちた。
――まさか、自分だけじゃなかったのか。
彩花は小さく頷き、目を伏せた。
「私、あの店で……昔の自分や、選ばなかった道を見たの。涙が止まらなくて」
「……俺もだよ」
悠真は拳を握った。
「“もしもの未来”で、俺は……高校の時に告白できなかった人と一緒にいた。ずっと心に残ってたんだ」
「そっか」彩花が空を見つめた
悠真の言葉は彩花には届いていなかった、だから
「君だよ…」と悠真は言った、
その瞬間、彩花の目が揺れた。
「……え、私?」
もう後悔なんてしたくない…だから
悠真は、黙って頷いた。
胸の奥に閉じ込めていた言葉が、ついに解き放たれた。
「俺、本当はあの頃からずっと……君に想いを伝えたかった。でも、できなかった」
彩花は黙って悠真を見つめた。
そして小さく微笑んだ。
「…私もね、少しは気づいてた、けど、関係が壊れそうで…怖くて聞けなかった」
カップの中のコーヒーはすっかり冷めていた。
けれど二人の心は、あの不思議な喫茶店で見せられた“もしも”と、今この現実とが重なり合って熱を帯びていた。
――あの店は、偶然なんかじゃない。
きっと人生の岐路に立った人間を導くために現れる場所なのだ。
悠真は深呼吸して、言葉を絞り出した。
「今度こそ、後悔したくない。彩花……また会ってくれるかな?」
彩花の頬が赤らみ、静かに頷いた。
夜の街灯の下で、二人はゆっくりと歩き出した。
その背後で、電柱の影にたたずむ無表情だったマスターが、ふと口元に微笑を浮かべ、お辞儀をした。
悠真が道端に捨てた「パラレルのチケット」を拾い上げ、低く囁く。
「いずれ、またのご来店をお待ちしています」
その声は蜃気楼のように揺らめき、夜の闇に溶けて消えた。
本ブログに掲載されている小説は、すべてフィクションです。 実在の人物、団体、事件とは一切関係ありませんのでご了承ください。
作品の著作権は、特に記載がない限り**作者 秋澄 美千子 **に帰属します。 引用の際は、著作権法で認められた範囲内でお願いいたします。
作品の無断転載、複製、配布、改変は固くお断りいたします。 これらの行為が発見された場合、法的な対応を取らせていただくことがありますので、ご注意ください。